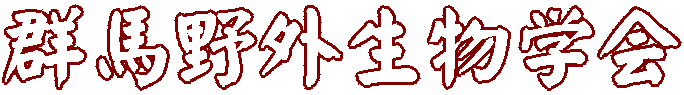|
2013年10月
|
|
〇小池沼に産するコケムシの一種について、(田村一利)
|
|
〇群馬県およびその周辺における要注意外来生物アカボシゴ
|
|
マダラと在来種の越冬幼虫個体数比較、(小林栄一・新井 武・下田 智・小池正之)
|
|
〇第2のヤリタナゴの生息地を造る、(斎藤裕也)
|
|
〇群馬県におけるニンギョウトビケラ属とコブニンギョウトビケラ属、(宮原義夫)
|
|
〇群馬県内のフジバカマの保全について、(石川真一・高橋美絵・青木良輔・松田紗依・荒川 唯・都丸希美・塚越みのり・浦野茜詩・春原悠樹)
|
|
〇関本平八と多々良沼―関本平八の日記から―(青木雅夫)
|
| |
|
2014年10月
|
|
〇群馬県およびその周辺における要注意外来生物アカボシゴマダラと在来種の越冬幼虫個体数比較2(小林栄一・新井 武・下田 智・小池正之)
|
|
〇タイリクバラタナゴを駆除してヤリタナゴの生息地とする(斎藤裕也)
|
|
〇県内の流水性コウチュウ類-ヒメドロムシの話題を中心として―(茶珍 護)
|
|
〇湯檜曾川沿いのセッケイカワゲラ類の種類と季節的消長(宮原義夫・土屋清喜)
|
|
〇群馬県のジョロウグモ(林 俊夫)
|
|
〇セアカゴケグモについて(林 俊夫)
|
| |
|
2015年10月
|
|
〇ヤリタナゴ原生息地の状況と移植個体群(斎藤裕也)
|
|
〇桐生市広沢町におけるツマグロヒョウモン成虫の発生消長(小林栄一)
|
|
〇外来種アメリカツノウズムシとアメリカナミウズムシを群馬県で記録する(掛川優子)
|
|
〇群馬県における雪カワゲラの分布(宮原義夫・土屋清喜)
|
|
〇県内各地で確認されるカワムツについて(斎藤裕也)
|
| |
|
2016年10月
|
|
〇群馬県におけるアサギマダラの発生消長と幼虫の食餌植物(小林栄一)
|
|
2017年10月
|
|
〇桐生市広沢町および太田市長岡町・菅塩町のモンシロチョウの世代数と個体数変化(小林栄一)
|
|
〇谷川岳付近の湯檜曽川沿いで見られる雪カワゲラ類と季節的消長Ⅱ(宮原義夫・土屋清喜)
|
|
〇環境水路(農業用水)に戻り始めた生物たちについて(掛川優子)
|
|
〇オオタカの捕食行動(谷畑藤男)
|
|
〇アキザキヤツシロランGastrodia verrucosa Blumeの自生地(青木雅夫)
|
|
〇榛名湖における甲殻類プランクトンDaphniaによる輪虫類プランクトンへの抑制の検証(栗田秀男)
|
| |
|
2018年10月
|
|
〇太田市西長岡街における2017年から2018年3月のいわゆる冬季のモンシロチョウ卵と幼虫 の状況(小林栄一・小池正之)
|
|
〇高山蝶ミヤマシロチョウ生息数調査と保全整備(宮﨑光男・松村行栄)
|
|
〇榛名湖における大型動物プランクトンDaphniaの輪虫類への抑制の検証(栗田秀男)
|
|
〇利根川のサケ遡上数の最近の変化(斎藤裕也)
|
|
〇群馬のスミレ(大平 満)
|
|
〇モリアオガエルの水から離れた産卵について(富岡克寛・廣瀬文男・金井賢一郎)
|
| |
|
2019年10月
|
|
〇群馬県太田市におけるナガサキアゲハ成虫の発生消長とその特徴(小林栄一)
|
|
〇高崎駅東口におけるムクドリの塒(ねぐら)の観察(谷畑藤男)
|
|
〇震災後の利根川のサケ(斎藤裕也)
|
|
〇群馬県で初確認された希少ゲンゴロウ,ガムシ類について(茶珍 護)
|
|
〇群馬県におけるコバントビケラ属幼虫の記録(宮原義夫・土屋清喜)
|
|
〇化石から見たウミサソリの誕生と絶滅(林 俊夫)
|
| |
|
2022年10月
|
|
〇群馬県の天然記念物―チョウを例に―(松村行栄)
|
|
〇アオバトの不思議(谷畑藤男)
|
|
〇利根川水系のサクラマス(斎藤裕也)
|
|
〇コバントビケラのくらし(宮原義夫・土屋清喜)
|
| |
|
2023年10月
|
|
〇みどり市桐原の自宅敷地内で確認できたクモ(林 俊夫)
|
|
〇烏川中洲におけるチドリ類3種の繁殖について(谷畑藤男)
|
|
〇桐生市広沢町5丁目自宅周辺におけるチョウ相(小林栄一)
|
|
〇カヤネズミの話(宮原義夫)
|
|
〇シマドジョウ卵の育ち方(相澤裕幸)
|
| |
|
2024年10月
|
|
〇カヤネズミの話(その2)(宮原義夫)
|
|
〇群馬県レッドリスト野生絶滅種ヤリタナゴの現状について(斎藤裕也)
|
|
〇海外のチョウ保全の事例紹介-リッチモンドトリバネアゲハ(オーストラリア)(松村行栄)
|
|
〇前橋市大渡橋利根川右岸にアカギツネを目撃する(井田宏一)
|
|
〇太田市菅塩町のクロコノマチョウ(小池正之)
|